一時期、「ちょっとしたことが決められない」と悩んでいたことがあります。
本当に些細なことで、「どのカフェに入るか」とか「どの歯医者さんに行くか」といった程度のものなんですが。今後サクサク決断していくために、読んでみました。
柳生雄寛『なかなか自分で決められない人のための「決める」技術』ディスカヴァー・トゥエンティワン Kindle版(2019)
広告- - - - - - - - - -
どんな本?
すぐに正しい決断ができれば、それだけやれることが増えるわけですから、仕事や人生がうまくまわるようになる、と著者はいいます。
では、
・決められない人と、さっさと決断できる人はどこが違うのか。
・そもそも「決める」とはどういうことか。
・決められるようになるにはどうしたらいいか。
また、決めるだけではダメで、決めたら続けることも必要になってくる。
・続けるにはどうしたらいいか
こういったことを紹介している本です。
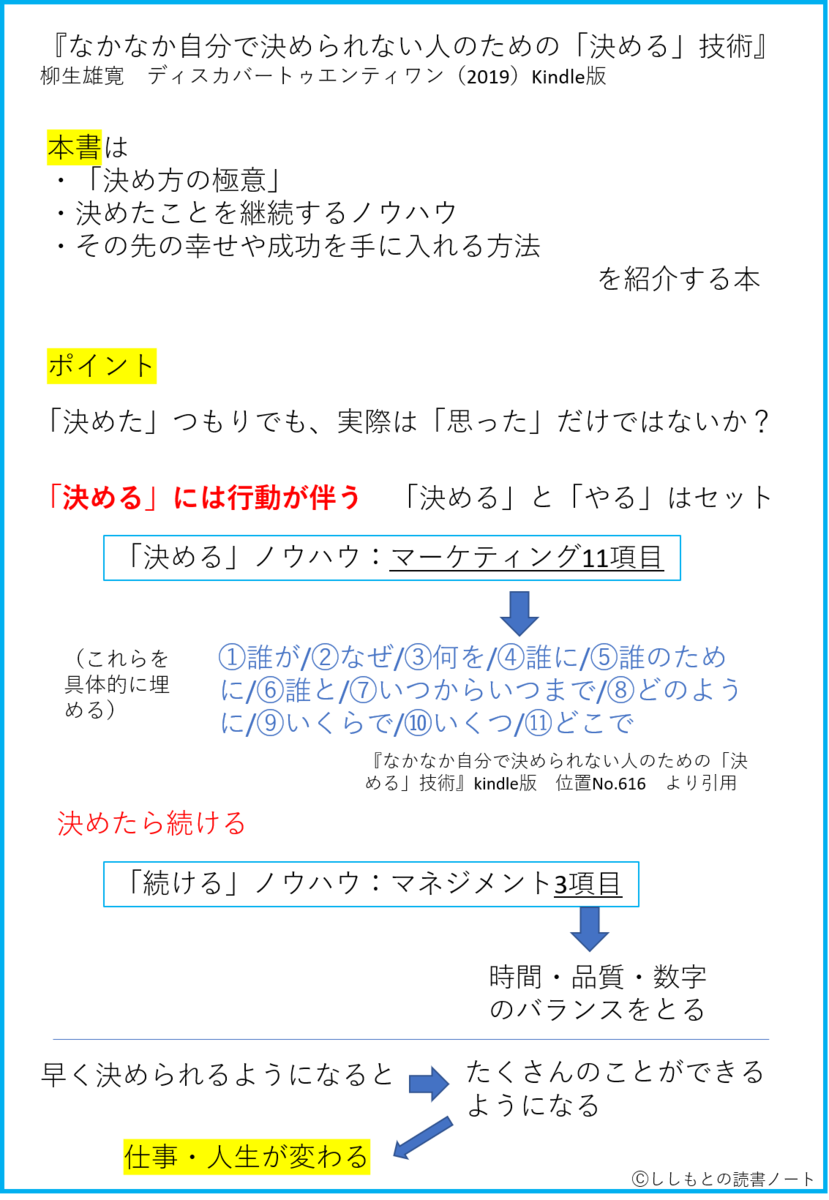
感想
そもそも「決める」とは
本書を読んでいて、私が一番ハッとなったのは、「決める」と「思う」を混同していないか? という指摘。
たとえば、「明日は朝早く起きて書類を作成しよう!」と思ったとします。
しかし、いざ起きてみると、いつもの時間だった、という経験は誰にでもあるのではないでしょうか?
これは「朝早く起きて書類を作成しよう」と「決めた」のではなくて、「思った」だけだと著者はいいます。
早起きが苦手な私、「明日は〇時に起きよう」と決めたのに……というくだり、超あるあるです。
「決めた」と思っていたけれど、「思っただけ」だったんですね……たしかに。
著者によれば
「決める」には行動が伴う
「決める」と「やる」はセット
とのこと。
そういえば、「絶対に遅刻できない」状況のときは、目覚まし時計を複数個かけていました(行動が伴っている)。
一方、「〇時に起きよう」程度のモチベーションだと目覚ましのアラームは一つ(止めてまた寝てしまう)。
まさに、行動が伴っていませんね……。
「意志が弱いだけ」「意志の弱さは気合で克服せねば」なんて漠然と思っていましたが、足りなかったのは意志というより「行動」だったんですね。
早起きに限らず、ダイエットやら運動習慣なども同じことがいえます。
「明日から〇〇しよう!」だけでは「思った」にすぎない。
具体的な行動も設定し、遂行する必要がある、というわけです。
このあたりの「決める」コツとしては、マーケティングの11項目を満たす、とのことで、詳細は本書をご確認ください。
今後は、「決めるんだったら、行動もセットだからね?」と自分に言い聞かせることにします。
意識するだけでもずいぶん違いそうな気がする。
「決めた」ら「続ける」も大事
「決める」は行動を伴うことですから、その行動を続けることも、大事になってきます。
しかし、決められない人は、続けることも苦手だそうで。
(私にも思い当たるフシが……)
続けるためのコツは、他の習慣化関連の本でも言われているように、「ハードルを下げる」「すでに習慣になっていることとセットにする」「数値化」などが挙げられていました。
簡単にいえば「続けられる条件に落とし込む」ということですね。
本書によれば、「時間・品質・数字」のバランスをとるとよい(=マネジメント)とのこと。
(本書ではマネジメントの説明として、「女性との食事」を例に挙げていました。
「時間(食事をする時間帯)・品質(味)・数字(金額)」のバランスをとり、(総合的に)喜んでもらうこと、的な)
ともあれ、「どうしたら自分は続けられるか」ということも、ある程度失敗してみないとわからないのかな、という気がしています。
ハードルを下げるにしても、どこまで下げたらよいか、下げすぎではないか、ということは、やってみないとわかりませんものね。
続けられなかったら、その都度再設定して、また続けてみたらいいのですよね。
(習慣化に関してこちらもどうぞ)
experience.shishimoto-yuima.work
experience.shishimoto-yuima.work
私の「ちょっとしたこと」が決められない原因を考えてみた
さて、冒頭で少し触れた、私の「ちょっとしたことが決められない」問題。
とりわけ些細な「どのカフェに入るか決められない」の原因を考えてみます。
本書第1章で、決められない人の特徴が多々挙げられているのですが、とくにあてはまるのはこれかな、と。
[決められない人] あれもこれもと欲張る
『なかなか自分で決められない人のための「決める」技術』Kindle版 位置No.212
それ。
カフェAは雰囲気が良いが、少しお高い。
カフェBはリーズナブルだが、ややチープな雰囲気。
カフェCは広くてかつリーズナブルだが、コーヒーの味が好みでない。
カフェDはリーズナブルだしコーヒーもおいしいが、混雑している。
カフェEは……(つづく)
といった感じで、「私の希望を100%満たすカフェ」に行こうとしていたんですね。
しかし、「私のために作られたカフェ」でないのだから、「希望を100%満たすカフェ」なんて、まあ、存在しないですよね。
ないのに、見つけようとしていたから、「どのカフェに入ろうか決められない」という状態に陥っていたのだ、と気づきました。
いやはや、何をやっているんだ、私は(恥)。
著者によれば、決めるには「一つに絞る」ことが大事とのこと。
他の選択肢を捨てきれていない、というわけなんですね。
今日はおいしいコーヒーが飲みたい気分だから、味優先、とか。
今日は作業したいから、落ち着いた雰囲気を優先、とか。
カフェに行く前に、何を優先するか、考えてから出かけよう、と思ったのでした。
広告- - - - - - - - - -
おわりに
「決めた」と思っていたことが、実は「思っただけ」だった、ということに気づかされたのは、大きな収穫でした。
「決めたのにできない」「やりたいのになぜかできない」というときは「具体的に行動してる?」と自分に問いかけようと思います。
どうしても「行動」ができない、というときは、それって実は「やりたくないこと」「やらなくていいこと」なのかもしれませんね。
